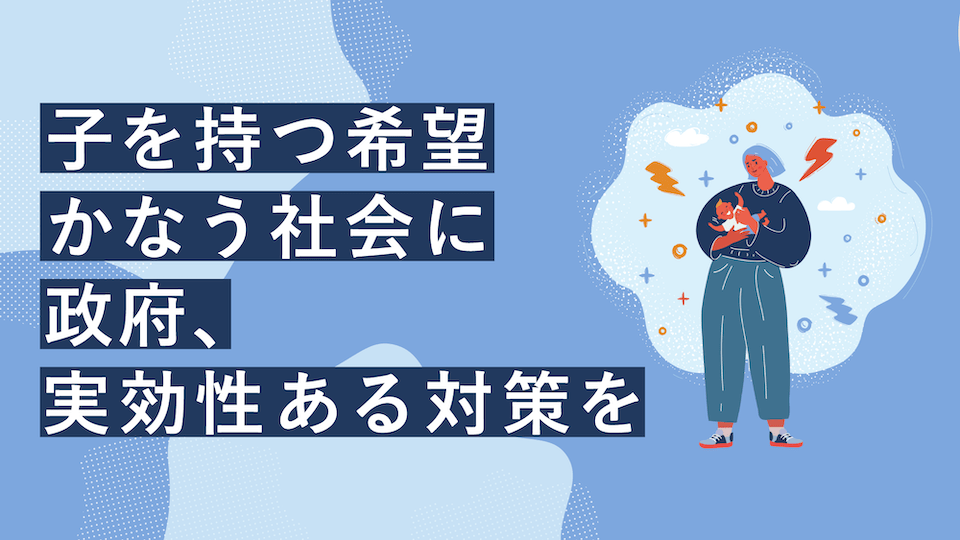
※この記事の内容は、弊社ゼネラル・パートナーの村上由美子が共同通信に寄稿したものです。
10年以上前のことだが、第3子を妊娠中に米国から日本に帰国することとなった。長男と長女を米国で出産したため、慣れぬ日本は不安であったが、予想以上に「産みやすい」環境が整備されており、感心した。
例えば出産休暇制度は米国でも存在するが、連邦政府レベルでは日本のように一定の給与支給は保障されていない。従って経済的な理由により、比較的短期間の産休を取得した後、職場復帰する女性が多い。育児休業は、日本の1年間の雇用保障に対し、米国は12週間である。
米国には、日本の認可保育園のような公立の保育施設もない。私の場合、上2人の子どもたちを出産した後、復職するには、高額のベビーシッターをフルタイムで雇うしか方法がなかった。
日本で生まれた次男は、生後4カ月で保育園に入れたのだが、その費用は米国のベビーシッター代の数分の1程度だった。保育の質にも感銘を受けた。経験豊富な保育士の方々に子どもを預けることができ、安心して仕事を続けられた。
日米を比較すると、日本で子どもを産み育てる制度は充実しているように思える。しかし2021年の日本の出生率は1.30と、米国の1.66をはるかに下回る水準だ。
米国の出生率が日本よりも高い最大の理由は、女性が社会に進出し、経済力を向上させたことではないだろうか。
通説
女性が高い教育を受けて社会に出ると、子どもを産まなくなるという通説をよく耳にする。事実、1960年代から70年代の米国や欧州で、そのような傾向が見られた。しかし近年の調査では、相関関係が反転していることが確認されている。
高等教育を受け、仕事で成功する女性の方が、より多くの子どもを産む可能性があるのだ。米労働市場の高い流動性と柔軟な雇用環境も、女性のキャリアアップに貢献していると考えられる。
年功序列により昇進が大きく左右される日本国内の環境は、出産などのライフイベントを経験した女性には不利になるケースが多い。勤続年数にかかわらず、成果が評価に直結する「ジョブ型雇用」が浸透すれば、日本でも男女共にキャリアの選択肢が増えるのではないか。
日本の少子化は、待ったなしの危機的な状況にある。迅速に取り組むべき具体的な例として、配偶者の控除に代表される税制上の問題がある。日本女性の社会進出を妨げてきた主な要因の一つであることに間違いない。
年収が一定以上になると、所得税の配偶者特別控除が満額適用されなくなったり、社会保険料の負担が生じたりする「年収の壁」を超えないよう、労働時間を減らす女性が増えている。
これでは、労働者不足の解決や賃上げに取り組む政府の方向性と矛盾した結果になりかねない。さらには、出生率向上に不可欠な女性の経済力や労働意欲をそぐことにつながる。
税制の中立性という観点からも、配偶者の控除は撤廃されるべきであろう。年金の優遇税制の見直しも、硬直的な労働市場の改善に寄与すると考えられる。
メス
大学を卒業して大企業で60歳まで勤務すると、2千万円超もらえる退職金が、10年勤めた後に自己都合で辞めた場合、200万円にも満たない。こうした制度が、日本企業の社員にとっての転職コストを押し上げている現状にメスを入れてしかるべきだ。労働市場の流動性は正規、非正規労働者の間の壁を取り除くためにも必要である。
多くの非正規労働者が抱える経済的不安が、結婚をためらわせる結果を招いている。私は仕事を続けながら、子宝に恵まれた。もし日本で就職していたら、3人の子どもを産んでいただろうか。米国から帰国後、長く日本に住むにつれて、そうでない人生を送っていたのでは、と思う機会が多くなった。
子どもを持つことを望む人々が、その希望をかなえられない悲惨な社会に日本を転落させてはならない。政府は3月末に、児童手当の所得制限撤廃などを柱とした「次元の異なる少子化対策」のたたき台となる試案を公表した。実効性をきちんと担保した政策にした上で、着実に遂行することを期待したい。