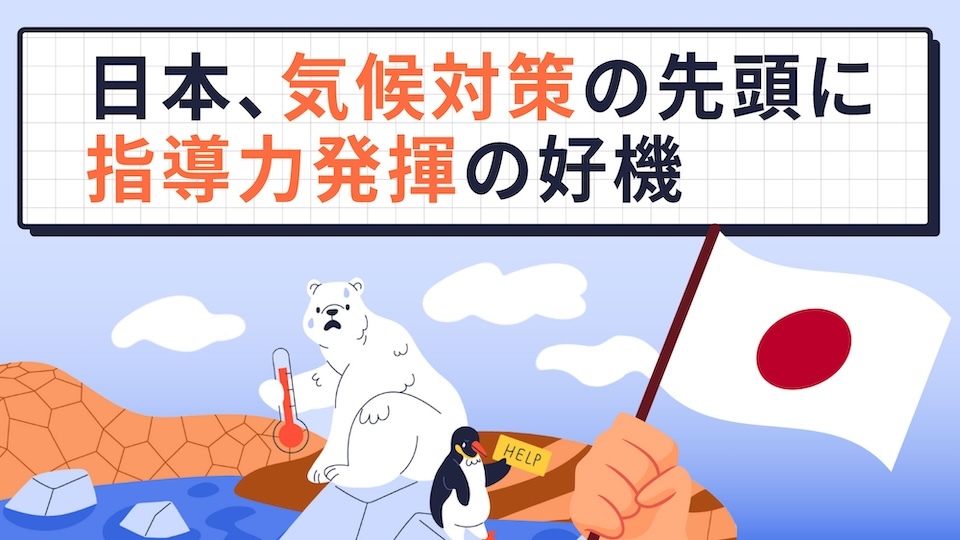
トランプ米大統領は気候変動対策の国際的な枠組み「パリ協定」からの離脱を決めた。世界最大の経済大国で、中国に次ぐ第2の温室効果ガス排出国でもある米国の協定離脱の影響は小さくない。国際社会の対応が問われている。
米、パリ協定離脱
パリ協定はリビアやイラン、イエメンなどを除く世界のほとんどの国が参加する、気候変動対策のための包括的な合意である。産業革命前からの気温上昇を1.5度に抑える目標を掲げて、参加国に温室効果ガスの排出削減を求めてきた。
しかし、気候変動対策に一貫して否定的なトランプ氏は、米国経済にとって不利になる国際協定であると主張している。さらに、同氏は環境保護に関する多くの規制の緩和を発表し、温室効果ガス排出量の多い化石燃料産業への投資を促進する方向性を明確に打ち出した。
トランプ氏は第1次政権の末期にもパリ協定を離脱した経緯がある。その後バイデン前政権時に復帰したため、離脱は一時的であったが、米国が当時拠出するはずだった負担金を他の参加国が肩代わりした。
欧州は温暖化対策を積極的に進め、世界に先駆けた野心的な政策を策定し、実施している。
日本も2050年に温室効果ガスの排出を実質ゼロにする目標を打ち出し、長期戦略を策定した。国内のエネルギー対策のみならず、発展途上国の気候変動対策への援助を通じて、地球規模の課題である温暖化問題解決への貢献を続けている。
環境ビジネス分野で近年、顕著に存在感を増しているのが中国だ。温室効果ガス排出量が世界で最も多い国である一方、排出削減に資する太陽光パネルや電気自動車(EV)産業を急成長させている。
パリ協定を含むグローバルな温暖化防止への取り組みに対する中国の資金提供は比較的低い水準にとどまるが、2国間ベースでの支援は際立っている。
米国が国際協調に背を向けて孤立主義的な政策を進め、気候変動対策においても、その国際的な存在感が今後薄れていくのは必至だ。半面、中国を含む他の国々にとって、同対策でリーダー的な役割を果たすチャンスにもなり得る。
途上国の期待大
こうした状況変化を日本の政官民は注視すべきだ。
前述した中国の積極的な資金支援が環境に配慮し、持続可能な開発につながっているのかという点に関しては見解が分かれている。特に途上国におけるインフラ開発援助の手法について、中国の環境配慮は不十分との指摘は多い。
他方、日本は質の高い援助を長年実施してきた実績があり、多くの途上国から高い信頼を得ている。特にアジア地域で温暖化対策を先導するリーダーとして、日本は中国以上に期待されている。
気候変動対策には多額の資金と長期にわたるコミットメント(関与)が必要とされるが、それは同時に環境関連市場におけるビジネスチャンスの創造にもつながる。
最先端テクノロジーを駆使した環境問題解決への期待は高まっており、アクセルを緩めた米国に代わって、日本が高い技術力を生かしてイノベーティブ(革新的)な解決策を生み出していくべきであろう。環境に関する技術の移転や人材育成などを通じて、日本がアジア諸国との連携を深めることも重要だ。
皮肉にもトランプ氏は、米カリフォルニア州ロサンゼルスで起きた大規模な山火事の発生から、それほど日を置かずパリ協定離脱を決めた。昨年秋には同氏の自宅があるフロリダ州を大型ハリケーンが直撃し、甚大な被害をもたらした。ほぼ同時期に、猛烈な勢いの台風が東南アジアを襲い、数百人の死者を出したとされる。
気候変動に伴い自然災害は年々、激甚化している。国連の気象専門家は昨年が観測史上最も暑い1年であり、世界全体の気温が産業革命以前と比べて1.5度強上昇したと発表した。米国不在となる中で日本は国際社会の先頭に立ち、人類の危機に直結する地球温暖化の阻止に向けて、強いリーダーシップを発揮してほしい。